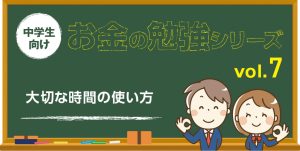お金の勉強シリーズvol.6
稼ぐ5 未来の仕事を考えてみる
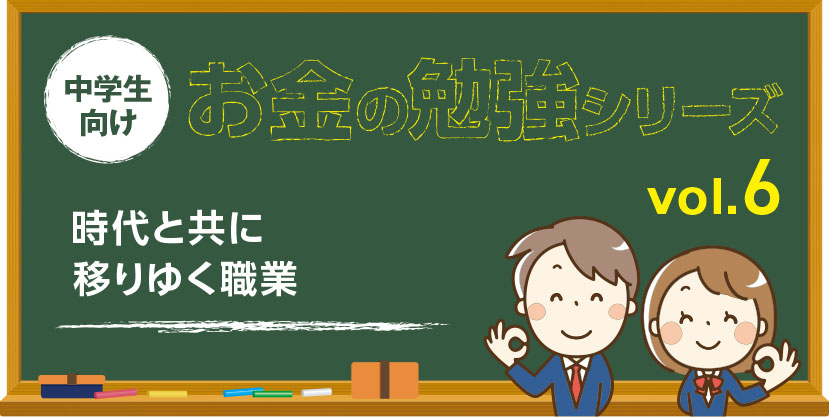
OECD(経済協力開発機構)では、労働力の中核となる生産年齢人口を15~64歳の人口と定義しています。世界との比較するときは、15歳~64歳の人口が何人いて、その国の何%に当たるかを調べます。
日本では,平成31年(2019年)1月分(3月 1日公表予定)からの公表冊子等において,我が国の労働力の中核となっている「20~69歳」 における労働力人口比率や就業率等の掲載を開始しました。
働く期間は、考えているより長いです。
その間には職業は変わっていきます。
今あるけれども50年前にはなかった職業。
・ユーチューバー
・プロのゲーマー
・携帯ショップ店員
・ネイリスト
・介護士

今はないけれども50年前にはあった職業
・電話交換手
・速記者
・タイピスト
・書生

今も昔も、多分未来もある職業
・教師
・医師や看護師
・政治家
・飲食業
・画家などクリエイター
・農業、漁業、畜産業

AIの発達によって「なくなる職業」「つくられる職業」も出てくるでしょう。イギリスに始まった産業革命で消えて行った職業があるように。
職業の中身も変わってくるでしょう。
ファミレスでロボットがお皿を持ってくるシーンを見るようになりました。
ファミレスは変わらなくても、仕事の中身は変わっていきます。
職業によっては、学歴・資格が必要なものもあります。
医師、看護師、教師など、何年も学校に通って資格を取ることが必要なものもあれば、設計士や建築士などのように資格も大事だけれど経験、実績が大切なものもあります。
そして、医師でも電子カルテの操作が必要になってきたように、求められるスキルは変わっていきます。
人生100年時代、1つの職業しか選べないわけではありません。
どの職業を選んだとしても、時代のアンテナを張り巡らせて、自分に必要なスキルを探し続けていくことは必要でしょう。
お金の基本は時代が移っても変わりません。

収入を得るためにはどうすればいいか
収入を得続けるにはどうすればいいか
今できることを考えていきましょう。
この記事の執筆者:三島 佳予子(Kayoko Mishima)
保有資格:CFP・1級ファイナンシャル・プランニング技能士 / 住宅ローンアドバイザー /宅地建物取
引士