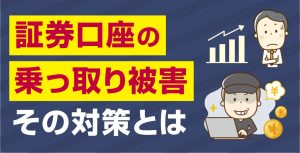暴落時につみたて投資はどうする?
目的と資産寿命を考える
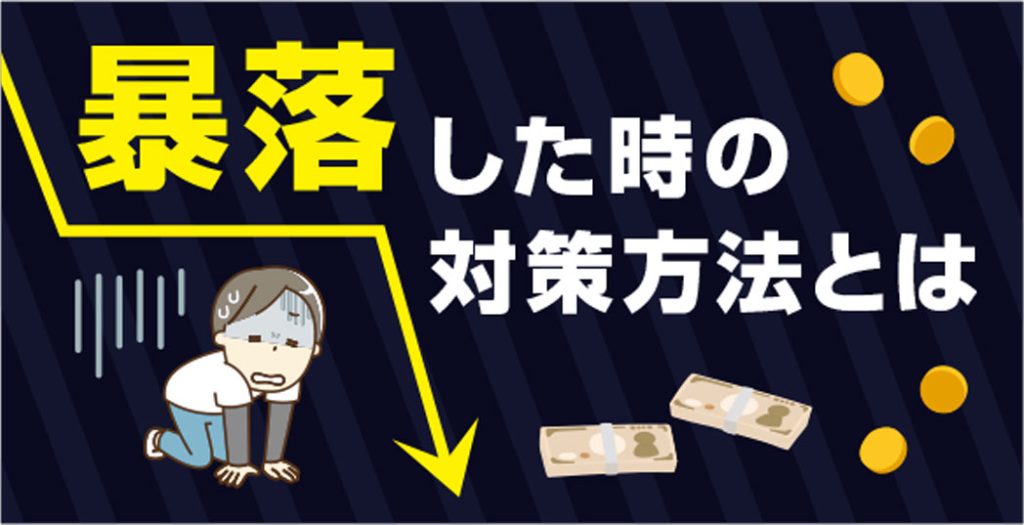
2024.01.01から始まった新NISAをきっかけとして、株式投資、積立投資を始めた方も多いでしょう。
2024年に入ってから日経平均株価は上昇してきましたが、2025年に入り一時4万円台だった日経平均株価が3万6千円台になるときもあり、2024年の新NISAをきっかけに投資を始めた方々にとっては「自分の資産が減る」体験をすることになりました。

つみたてNISAで人気が高いS&P500を指標にした投資信託やeMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)なども2025年に入ってから値を下げています。アメリカの主な経済指標であるダウ平均株価も同様です。

銀行預金(貯金)では、利子が少なくなることはあっても、「預けたお金が減る」ことはありませんでした。新NISAが対象としている株式投資は、自分の資産が増えたり・減ったりするものです。
数学的にみると、増えることも・減ることも、同じようにリスクと言われます。リスクとは「変動する」ことです。
けれど人は、増えた時の喜びよりも、減った時に大きな恐怖を感じるものです。頭では「変動するもの」と理解していながらも、実際に株価暴落など資産が減っていく恐怖を感じた時はどうすればいいのでしょう?
動揺するときは「基本に立ち戻る」ことが第一です。
それは、「運用しているお金はいつ使う予定のお金か」ということです。
株価は資本主義経済が発展していくと、長期では上昇していくものと言われています。長期の日経平均株価をみていると、バブル崩壊から30年以上かかりましたが日本の平均株価は上昇しています。

そして、つみたて投資は投資信託の基準価格(価値)が下がったときには、持っている資産も目減りするけれども、同じ金額でたくさん買うことができます。
3万円で基準価格1万円のときに買うと、3口買える。

3万円で基準価格5千円の時に買うと、6口買える。
(ただし、今まで買っていたものの価値は半分になり資産が目減りしている)

なので、コツコツと買い続けていく(つみたて投資をしていく)と、いずれ基準価格が上昇したときに利益がでる、というのがつみたて投資(リスクの時間分散)の考え方です。
だから、株価が変動してもコツコツ続けるのが王道です。
ただ、いつ上昇するのかは予想がつきません。
なので、投資は余裕資金で、長期運用でといわれるのです。
1カ月先の食費
1年先の修学旅行費用
3年先の学費
など、どうしてもこの時期に必要なお金を投資で増やそう、というのは危険です。必要な時期が資産の目減りするタイミングかもしれません。
また、老後資金をつくるための長期運用であっても、老後はいつからか、資産寿命をどのくらいに考えるかは大事です。
老後資産の取り崩し時期を70歳からと考えると
20歳で始めると、50年の運用
30歳で始めると、40年の運用
40歳なら30年、50歳なら20年、60歳なら10年、65歳で始めると5年で取り崩しを始める予定になります。
自身の年齢、先々の予想が大切になります。
資産の暴落時にこそ、「このお金はいつ・何のために使うお金か」の基本に立ち戻り、自身の年齢や資産寿命を考えながら、長期で運用するものならコツコツ続ける。これがつみたて投資との付き合い方です。
この記事の執筆者:三島 佳予子(Kayoko Mishima)
保有資格:CFP・1級ファイナンシャル・プランニング技能士 / 住宅ローンアドバイザー /宅地建物取
引士